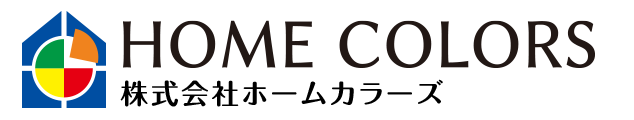【大阪市】建ぺい率・容積率って何?
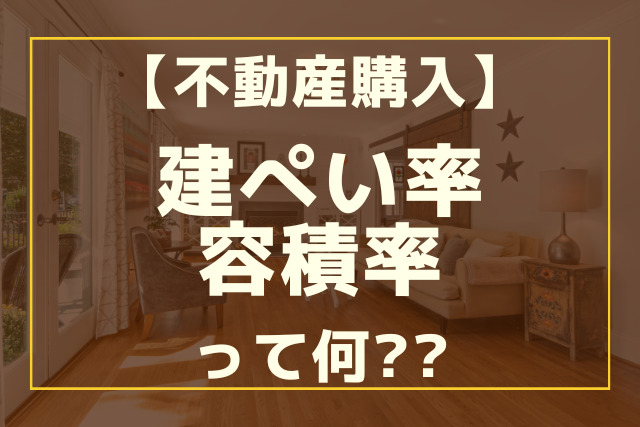
不動産を購入するにあたり、土地と建物の広さは最も重要なポイントの1つではないでしょうか?
しかし、土地の広さに対して建てられる建物の大きさは法律で様々な規制が設けられています。
その中でも今回は「建蔽(けんぺい)率」と「容積率」について詳しく解説したいと思います。
目次
- ○ ●建蔽(けんぺい)率
- ○ ●容積率
- ○ ●床面積に含まれない部分
- ○ ●まとめ
- ○ ●過去参考ブログ
●建蔽(けんぺい)率

◆敷地の面積に対する建築面積の割合
計算方法:建ぺい率=(建築面積÷敷地面積)×100
【例】建ぺい率60%、100㎡の敷地の場合
60%=(60㎡÷100㎡)×100
60㎡の建物が建築可能ということになります。
建ぺい率は敷地に一定の空間を設けることで建物の通風・採光を確保する目的と、火災の際には延焼しにくくなるよう防火の観点から定められています。
また建ぺい率の上限は用途地域ごとに定められています。
※用途地域:計画的な市街地を形成するために、用途に応じて13地域に分けられたエリア
◆建ぺい率:30・40・50・60%の用途地域
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・田園住居地域
◆建蔽(けんぺい)率: 50・60・80%の用途地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
●容積率
◆敷地の面積に対する建築可能な延べ床面積の割合
※延床面積=総床面積
容積率は建ぺい率と同じく住環境を保つだけでなく、人口制限をする役割もあります。
平屋や2階建ての住宅地に高階層の家が建つと近隣の日当たりや通風に影響するだけでなく、人口が増加し、インフラの供給が追い付かなくなってしまします。
そのようなことがないように住環境を保護しつつ、建築物と公共施設のバランスを保つ重要な規定です。
◆容積率:50,60,80,100,150,200%の用途地域
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・田園住居地域
◆容積率:100,150,200,300,400,500%の用途地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
※前面道路の規定に該当する土地に関しては、前面道路の幅員に用途地域による係数(0.4または0.6)を乗じて容積率の上限を算出すると定められています。
●床面積に含まれない部分

一定の要件を満たせば床面積に含まれない部分があります。
それらをうまく利用することで建築面積をできるだけ広く確保することも可能です。
◆ベランダ・バルコニー
壁から2m以内の部分は床面積に含まれません。2mを超えた部分は床面積に加算されます。
◆ロフト・吹き抜け
天井までの高さが1.4m以下ではしごが固定されていないロフトは床面積に含まれません。
なお、ロフトの面積は、ロフトがある階の1/2以下の面積であることが条件となります。
また、吹き抜けは床面積に含まれません。
◆外部階段
外付けの外部階段は延床面積には含まれません。外部階段の面積の分、広い建物を造ることができます。
◆地下室
住宅の用途に供する部分で、地階であり地盤面から天井が高さ1m以下かつ総床面積の1/3を限度として容積率に含めず建築可能です。
●まとめ
大阪市北区で不動産の購入・売却をご検討の際はLIXIL不動産ショップホームカラーズへ
地元出身、不動産歴30年以上のベテランスタッフが不動産に関する様々なご相談に親身に対応させていただきます。
ぜひお気軽にお問合せ下さい。